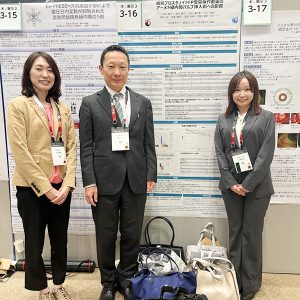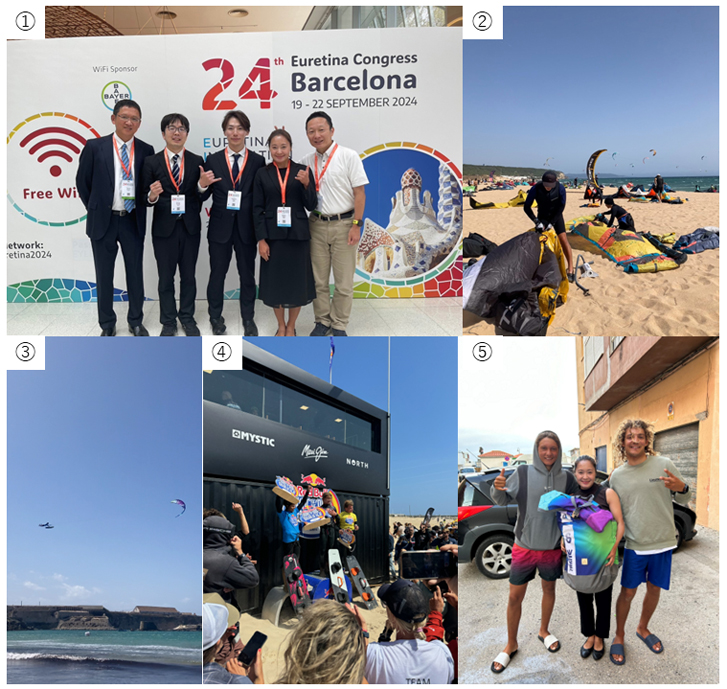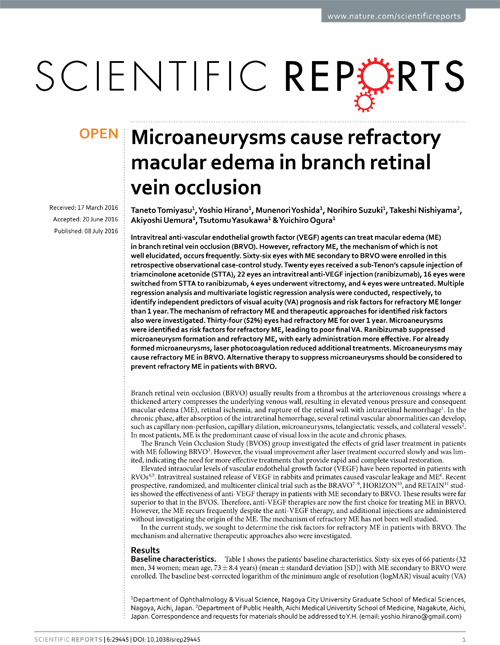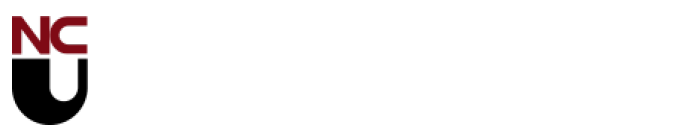2025年10月6日
『25th Euretina Congress Paris 2025』
シニアレジデント 早見 拓真(R4)
この度、2025年9月4日~2025年9月7日にフランス・パリで開催された25th Euretina Congressに参加する機会を与えていただいたため、ご報告いたします。
Euretinaは、毎年ヨーロッパの各地で開かれる世界規模の網膜学会の一つです。会場には世界中から眼科医・研究者が集まり、最新の知見や治療法についての議論を直接聞くことができる貴重な場でした。初めての海外学会の参加でしたが、英語での発表や質疑のテンポの速さに圧倒されつつも、学問の最前線に触れることができました。会場では様々な分野の講演を聞いたり、機械展示をみたりと、有意義な時間を過ごしました。理解できない場面も多々ありましたが、大変充実した時間となりました。
私自身は、「増殖糖尿病網膜症に対する27ゲージ硝子体手術の治療成績と合併症の検討」についてポスターを提出しました。当院における2015年から2024年までの27ゲージ硝子体手術について統計をとり、25ゲージ手術のデータと比較しました。これも初めてとなる英語でのスライド作成であり、8枚以内とコンパクトな指定でしたが、英語の言い回しや表現について調べつつ、見やすいスライドを意識して作成しました。最後には平野先生にもご指導いただき、完成することができました。
また今回は、同期の山崎先生と河合先生もそれぞれポスターを提出していますが、山崎先生が安川教授指導の元に提出した題材が、本年度のEuretinaより新設された「e-Poster Theatre」に選出され、ポスターの内容について口頭発表を行いました。医局内でも予演会を通して練習を重ねており、本番はかなり緊張があったと想像しますが、無事発表を終えられていました。
学会場の展示ブースでは最新の手術機器や検査器械に触れることができました。印象的だったのはスマートフォンに装着する形で使用する無散瞳広角眼底カメラで、企業担当者が丁寧に説明してくれ、実際に操作体験させていただきました。
学会後には、凱旋門やエッフェル塔、ルーブル美術館などのパリの観光地や美術館を訪れ、学びと文化体験を両立する有意義な時間を過ごすことができました。学会という非日常の場だからこそ、学習・研究へのモチベーションを新たにする契機になったと感じています。
最後になりますが、このような機会を与えてくださった安川教授をはじめ、忙しい業務の中ご指導賜りました平野先生、および医局の諸先生方に対し、この場をお借りしてお礼申し上げます。